サンサーンスの交響曲3番、通称「オルガン」。
オーディオのデモとしても良く使われる作品の1つです。
数ある録音の中でも、演奏の質と録音の素晴らしさの両面で筆頭に挙げられる一枚です。1970年代アナログ録音の金字塔と言えます。
Louis Fremaux - Saint-Saens: Symphony No. 3
EMI - TWO 404

この歴史的な録音は、1972年に英国のバーミンガム大学グレート・ホールにて行われました。
指揮はフランス音楽のスペシャリスト、ルイ・フレモー、管弦楽は彼が音楽監督を務めていたバーミンガム市交響楽団、オルガンはクリストファー・ロビンソンが担当しています。プロデューサーはデヴィッド・モトリー (David Mottley)、そしてバランス・エンジニアを務めたのが、伝説的なスチュアート・エルサム (Stuart Eltham) でした。
録音の背景には、フレモーがCBSOを率いた1969年から1978年にかけての「黄金時代」があります。彼はこのオーケストラを英国有数の一流アンサンブルへと変貌させ、その功績は後任のサイモン・ラトル (Simon Rattle) が「世界最高のフランス管弦楽団」と評したほどでした。
EMIがDeccaの「フェイズ4ステレオ」に対抗して立ち上げた高音質レーベル「Studio 2 Stereo」シリーズの一環として制作されました。サウンドは、「深く、そして明瞭なオルガンの低域」が特徴です。他の有名作品と比べて、低域の音階がしっかりと収録されています。
アナログ時代だと、リヴィングステレオからのミュンシュ&ボストン響 (LSC 2341)の評価が高いですが、野暮ったく聞こえて好みではありません。
オーディオデモでは、テラークのオーマンディー&フィラデルフィア管 (DG 10051)が使われることが多いです。
それと比べても、このフレモー盤のクライマックスでのエネルギーの塊は、この作品の頂点にふさわしい録音です。音圧よりもその低域の分解能が凄くて、これを聴いた後にミュンシュを聴くと音が団子状態に感じます。
あとは、マーキュリーのパレー&デトロイト交 (SR 90012)、EMIのプレートル&パリ管(ASD 585)でしょうか。
Deccaのアンセルメ盤 (SXL 6027)はそれらに比べるとやや不利に感じます。
引用した他の作品と比べても入手性は高いので、最初に買うオルガンとしてお勧めです。
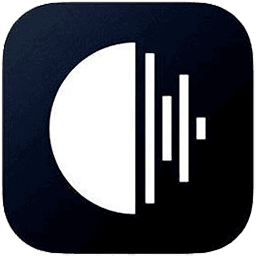 Roon
Roon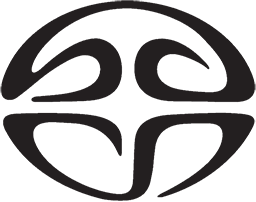 SACD
SACD
コメント