「このCDは録音レベルが高すぎて音が潰れている」「音が極端に左右に振られているな」。普段音楽を聴いていると、そんな感想を抱くことがあります。しかし、なぜ制作者はそのような音作りをしたのでしょうか。
私自身は演奏も録音もしないため、その道のプロが書いた本は、新たな発見を与えてくれる貴重な情報源です。今回は、そうした「なぜ?」を解き明かし、制作者の意図を読み解く面白さを教えてくれる書籍「とーくばっく ~デジタル・スタジオの話~」を紹介します。
とーくばっく ~デジタル・スタジオの話~

現在は一般の書店では販売されていないようです。
著者の方から直接購入しました。
自身の経験が、知識で裏付けられる喜び
本書は、録音に関する実践的な知識を分かりやすく解説しています。例えば、私がレコードをデジタル化する際の話です。最終的にCDフォーマット(44.1kHz/16bit)にする場合でも、一度ハイレゾ環境(96kHz/24bit)で録音してから変換する方が、音が良いと感じていました。本書ではその理由がデータと共に説明されており、自分の感覚が正しかったと裏付けられたことは、大きな収穫でした。
また、言葉は知っていても役割が曖昧だった「ディザリング」の意味など、基本的ながら重要な知識を再確認できたのも有益です。
長年の疑問が解けた「M/S処理」の話
録音する人には当たり前のことかもしれませんが、個人的に最も興味深かったのは「M/S処理」で生じる位相の問題です。
ロック系の作品で、ボーカルが中央に、ギターなどが左右に配置されているのに、なぜか楽器の音にボーカルが埋もれて「中抜け」したように聴こえることがありました。本書を読み、その原因がM/S処理による「位相が回る」という現象で説明できると知り、長年の疑問がすっきりと解決しました。
このように技術的な背景を知ることで、制作者が意図した音なのか、それとも意図せずそうなったのか、と思いを巡らせることができます。これは、音楽の新たな楽しみ方です。
本書は専門家向けではなく、オーディオが好きな方や、音楽をより深く味わいたいと願うすべての人にとって、面白い発見がある一冊だと感じます。
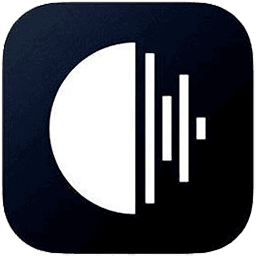 Roon
Roon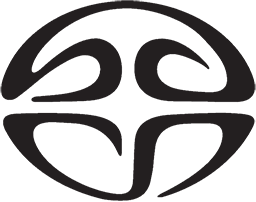 SACD
SACD
コメント