バッハの無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータという作品は、ヴァイオリン独奏を代表する作品です。
それこそ、ヴァイオリン奏者であれば、避けられない作品ではないでしょうか。
現時点で最も愛聴しているのは、カール・ズスケです。
ズスケのキャリアは、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団、ベルリン国立歌劇場、そして国営レコードレーベル「エテルナ」といった、東ドイツの最高峰の音楽機関の内部でほぼ完結しています。
政治的には制約があったものの、手厚い国家の補助を受けた東ドイツの芸術環境は、西側の商業主義や流行とは一線を画す、独自の芸術的価値観を育む土壌となります。
個人の技巧を誇示するよりも、作品の構造的完全性、目的の真摯さ、そして集団としての統一性を重んじる「ドイツ的」とも言える演奏様式を醸成させます。
ズスケが後に東ドイツ国家賞を授与されたことは、彼がこの国家公認の文化的理想の体現者として高く評価されていたことの証明です。
彼の演奏が「誠実」で「飾り気がない」と評されるのは 、実質を重んじた東ドイツ時代の芸術文化全体の美学を反映しています。
Karl Suske - Bach: Sonata and Partita No. 1
Eterna - 827 842

バッハの無伴奏全集は、1983年から1988年にかけて、5年という長い歳月をかけてドレスデンのルカ教会でセッションが組まれました。
決定的に重要なのは、その間に録音技術がアナログからデジタルへと移行したことです。
1983年に行われた最初のセッション、ソナタ1番とパルティータ1番の録音は、伝統的なアナログ方式です。これが、LPとして先行リリース(Eterna 827 842)されました。
その後、プロジェクトが再開された1985年から1988年にかけて録音された残りの4曲、ソナタ2番、パルティータ2番、パルティータ3番、そしてソナタ3番は、すべてデジタル録音です。
プロジェクトがまだ完了していない段階で、完成していたアナログ録音部分を単独の製品としてリリースすることは、レーベルにとって極めて合理的な判断だったのかもしれません。
他の評価の高い演奏と比較し、ズスケは非常に地味です。
ただ、それは個の主張をせずに、作曲者の意図した表現に徹しているように感じます。色々と聴いても、結局ズスケに戻ってしまいます。
バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、そのどれを聴いてもそのように感じます。私は無神論者ですが、ズスケの演奏は神の存在を感じます。悟りの境地に近い感覚です。
少し前までは東独エテルナのレコードが再プレスされたり、SACDでリリースされるとは思っていませんでした。
この無伴奏も枚数限定でレコード化されました。
そして、デジタル録音の2番、3番も初のレコード化です!
参考: [タワレコ] J.S.バッハ: 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ&パルティータ全曲
ズスケの全集を聴いていると、アナログ/デジタル録音のハイブリッドでありながら、シームレスで違和感を感じることはありません。
この無伴奏はで使用されたヴァイオリンはなにか知りませんが、彼にはおもしろい逸話があります。
1994年に来日したズスケの演奏会を聴いた、ヴァオリン制作者は、その「美しい」響きに深く感銘を受け、当然のようにストラディヴァリウスやガルネリといったイタリアの名器が奏でているものと思い込んでいました。
しかし演奏会後の会食の席で、ズスケ本人から、そのヴァイオリンが東ドイツ・ハレの弦楽器製作者ヨアヒム・シャーデによって作られた、製造後30年も満たない比較的新しい楽器であることを聞かされ、衝撃を受けたそうです。
参考:カール・ズスケさんに教えてもらったこと …。 | 自由ヶ丘ヴァイオリン
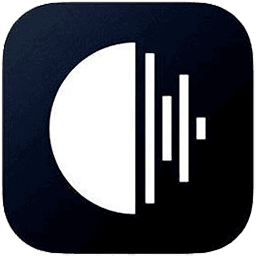 Roon
Roon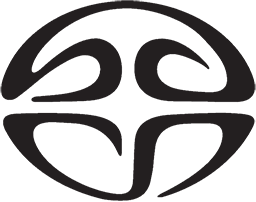 SACD
SACD
コメント